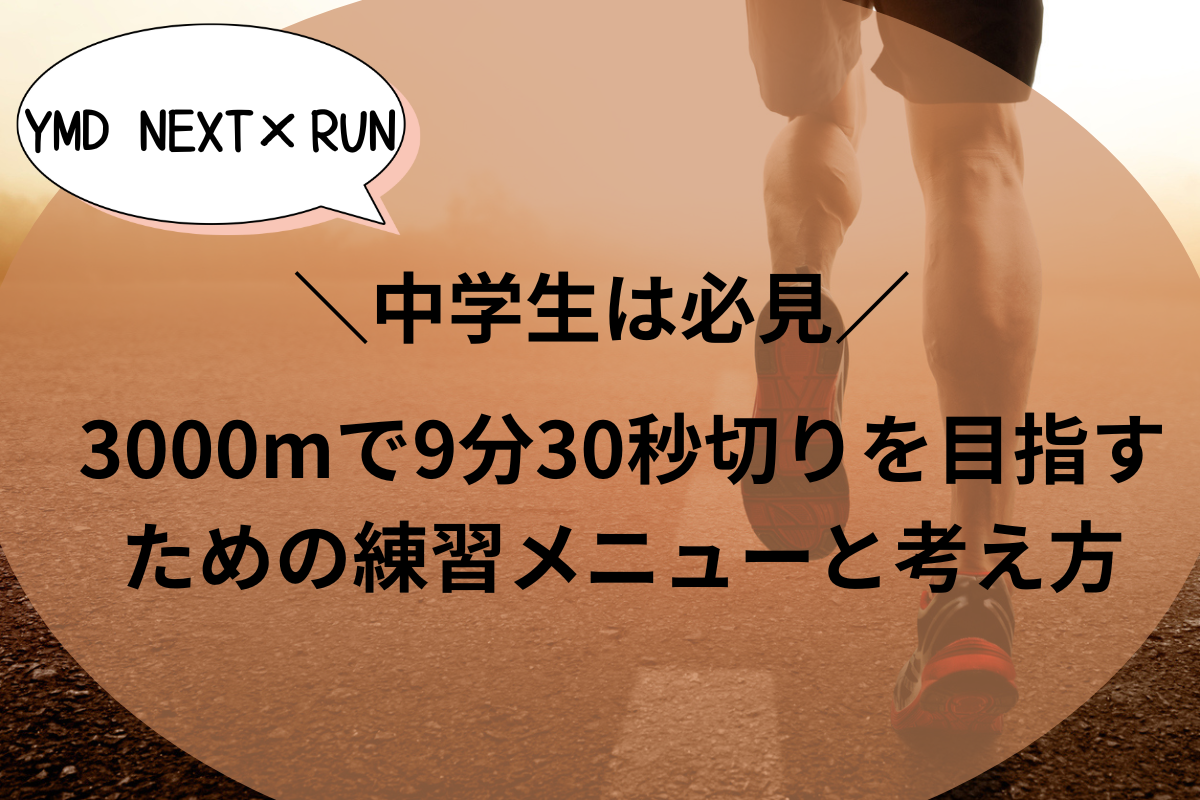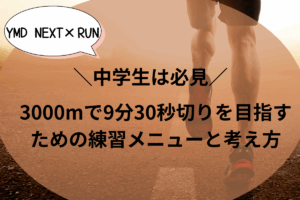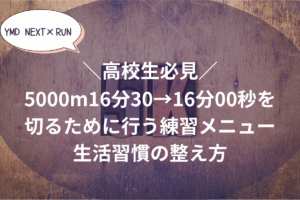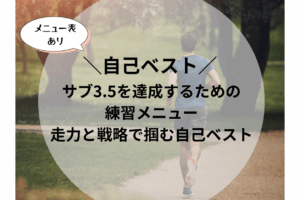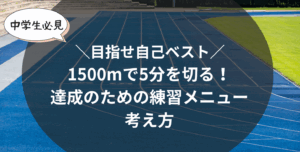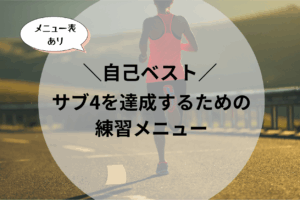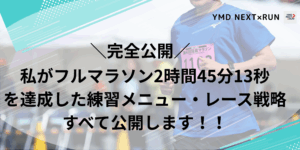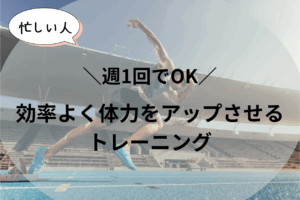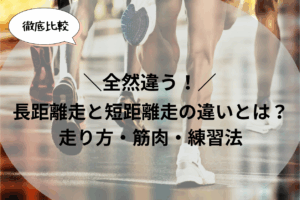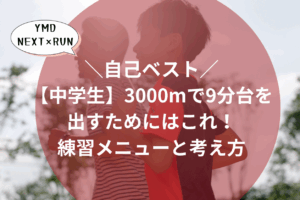はじめに
はじめまして。私は、「YMD NEXT×RUN」というオンライン型ランニングクラブを立ち上げ、全国の中高生から一般ランナーまで、幅広い世代に向けて練習サポートを行っています。
自身は中学・市立船橋高校・駒澤大学・実業団(富士通)で陸上競技を経験し、箱根駅伝やパリマラソンにも出場しました。引退後もランニングを続け、地域の大会では招待選手として走らせていただいています。
このブログでは、これまでの経験や指導で培ったノウハウをもとに、ランナーの皆さんが「次の一歩」を踏み出せるような情報をお届けしています。

\3児の子供たちのパパランナー/
【実績・経歴】
・香取市山田中学校
県大会優勝、県駅伝区間賞
・市立船橋高校 (体育科専攻)
県大会優勝、インターハイ出場
・駒澤大学 (文学部心理学科専攻)
2009年箱根駅伝第4区出場、関東インカレ決勝進出
・富士通株式会社
大田原マラソン第3位、パリマラソン17位(アジア1位)
引退後は社業に専念。会社員をしながら市民ランナーとして活動。「人の役に立ちたい、力になりたい」という思いから、YMD NEXT×RUNの指導を展開中。
3000mで9分30秒を切る。この目標は、中学生や高校生にとって全国大会や県大会上位入賞の基準タイムの一つとも言えるラインです。1kmあたり3分10秒、400mなら76秒前後で7周半を走る必要があり、持久力だけでなくスピード持久力・乳酸耐性・心肺機能など、バランスの取れたトレーニングが求められます。
ちなみに私が9分30秒を切ったのは中学2年生の10月、県新人の時でした。そこからは他校の選手が声をかけてくれるようになったり、他校友達ができたり。強い選手の仲間入りができたのかなと当時感じたのを今も覚えてます。
さて、この目標に向かって日々努力しているランナーに向けて、この記事では具体的な練習の考え方と1週間のメニュー例を解説していきます。
この記事を読めば以下が解決します。
・あなたの現状と課題
・ 9分30秒を切るための具体的な練習メニュー
・食事・睡眠の整え方
・モチベーションを保つコツ
🎉 中学生~大学生限定!初月無料キャンペーン
現在、未来あるランナーを全力でサポートするために、 中学生~大学生を対象に「初月無料キャンペーン」 を実施しています。
部活動や自主練習ではなかなか得られない、専門的なトレーニングや的確なアドバイスを体験できるチャンスです。
現状把握:まずは自分を知ることから
本記事では「現状把握」と「目標設定」の詳細は割愛しています。
それぞれ別記事で詳しくまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください。
◆ 3000m 9分30秒=どんなペース?
- 1kmあたり:3分10秒
- 400mあたり:約76秒
- ラップ配分例:3’10 → 3’10 → 3’10(イーブンペース)
| 種目 | 目標となるタイム | 自分の記録 |
|---|---|---|
| 1500m | 4分25~30秒 | 〇分〇秒 |
| 1000m | 2分55秒~3分00秒 | 〇分〇秒 |
| 2000m | 6分10秒 | 〇分〇秒 |
| 3000m | 9分29秒 | 〇分〇秒 |
ポイント
・タイムはあくまで目安です。スタミナ型で月間距離を踏めている人は多少これよりタイムが遅くても大丈夫。スピード型で、月間距離が踏めていない人はもっと速いタイムを目指すようにしましょう。
・月間走行距離の目安は300km程度といったところでしょう。
まずは、現在地を明確にしましょう。特に「どこでタイムが落ちるか」「ペース配分は適切か」「練習量は足りているか」を振り返ることが重要です。
そして、現状を正しく知ることは「ピーキング力(大会本番やポイント練習の時にベストな状態で臨む力)」を高める鍵でもあります。むしろ長距離はこのピーキング力だけです!自分の体がどんなときに調子が良く、どんなときに不調になるのか──中学校の大会の数、公式大会の数は限られており、数少ないチャンスを確実に掴まなくてはなりません。これを知れた人が、大会や重要な練習に向けて最高のパフォーマンスできるようになります。
目標設定|ここからがスタートです
目標設定は、練習の方向性を明確にし、モチベーションを高めるためにとても重要です。具体的な目標があることで、今自分になんのために練習をしているのか、なにが足りないから(なにを伸ばしたいから)この練習が必要なのか。が見えてきます。また、小さな目標を積み重ねていくことで達成感を得やすくなり、継続の力にもつながります。漠然と走るのではなく、「いつまでに何を達成したいのか」を定めることで、練習の質が大きく向上します。目標は成長の道しるべです。
目標設定のポイント:
- 長期目標:大会、記録会があるのが主に4月~7月、10月~12月だと思います。
まずは長期(6か月)での達成を目指してみましょう。目標レースを6か月前から逆算して練習計画を立てます。 - 中間目標:3カ月目で1000m2分55秒を目指す。4カ月目で2000m6分10秒前後を目指しましょう。
- 短期目標:前半は走行距離をたもちつつ、スピード練習を徹底的に行っていきましょう。
💡ポイント
大前提ですが、、筋肉の作りとして、(速筋・白筋)スピードをつければ持久力は落ちる。(遅筋・赤筋)持久力を上げるとスピードは落ちます。大事なのは、スピードと持久力のバランスです。
スピードさえつけば、距離を伸ばす(スピード持久力)のは比較的容易です。まずは前半はスピードをつける。後半は距離を伸ばしつつ、スピードも維持することを意識してください。
1週間の練習メニュー例
30秒を狙うための練習では、1週間の中に以下の4つの要素をしっかり取り入れる必要があります。
- インターバル走:レースペースでのスピード持久力養成
- ペース走:ペース感覚をつかむ練習
- レペティション:スピード刺激・フォーム矯正
- ロングジョグ:土台となるスタミナ作り
加えて、ジョグ・補強・ストレッチなどの「つなぎ練習」や「疲労回復」も軽視してはいけません。
また、以下の練習メニューはあくまで例です。時期、体調(疲労度)、天候、などあらゆる条件から練習を使い分けます。
| 曜日 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 月 | オフまたは軽めのジョグ | 回復・疲労抜き |
| 火 | ペース走5km(4”00程度)+1000m+400m | 中強度の持続力向上+スピード刺激 |
| 水 | ジョグ+流し(100m×3〜5) | 調整とフォーム確認 |
| 木 | インターバル走(1000m×4、2000m×2本など) | スピード持久力強化 |
| 金 | ジョグ+補強トレ | 基礎作り・疲労調整 |
| 土 | レペティション(400m×10など) | スピード刺激・リズム感養成 |
| 日 | ロングジョグ(12〜16km) | 有酸素・脚作り |
各ポイント練習の詳細
1000m×4
- ペース:3分05〜3分10秒/本
- リカバリー:200〜400m jog(1分00〜1分30)
- 意識ポイント:
- ペースを守りつつ、フォームを維持
- ラスト1本まで粘れる集中力
変化をつけたいときは800m×5、1200m×4、600m+400mの変化走なども効果的です。
2000×2本
- ペース:3分05〜3分10秒/本
- リカバリー:5分~10分
- 意識ポイント:
- ペースを守りつつ、フォームを維持
- ラスト1本はペースアップ
ペース走
- 距離:20分間走 or 4〜5km
- ペース:3分50〜4分00秒/km
- 特徴:
- 「ややきつい」強度(会話が難しい程度)
- 乳酸の閾値向上で“粘れる体”をつくる
- フォームとリズムを崩さずに走るのが鍵
+1000m+400mは80%から90%程度でリズムよく。
レペティション(400m×8など)
- ペース:72〜74秒/400m
- リカバリー:200m jog or rest(90秒前後)
- 目的:
- スピード刺激+動きのリズムづくり
- レーススピード以上でのフォーム確認
この日は心肺への負担は最大限にし、効率の良い走りの獲得を目指しましょう。
ロングジョグ(12〜16km)
- ペース:5分00~6分00/km
- 目的:
- 有酸素能力向上
- 筋持久力やメンタルの鍛錬
- 「長く走る」ことで走る体をつくる
友達と会話をしながらで構いません。この日を継続することで、ポイント練習での負荷にも耐えられるようになります。
3000m9分30秒切りスピード練習メニュー6パターン
3000m9分30秒=1kmあたり3分10秒ペース。
これを余裕を持って走り切るには、インターバルでスピード持久力を高めることと、レース後半の粘り(乳酸耐性・回復力)を鍛えることがカギとなります。
以下では6つの代表的なパターンを紹介します。
✅パターンA|王道インターバル:1000m×5本
- 内容
1000m × 4本(設定:3’05〜3’10)
リカバリー=200〜400m jog(約1~2分前後) - 解説
レースペース付近のスピードで繰り返し走ることで「目標ペースを身体に染み込ませる」練習。
距離も長く、本数も多いため、持久力とスピード両方の基盤を作る最重要メニュー。
週1回〜2週に1回、必ず取り入れたい基本形です。
✅パターンB|レース後半対応力:600m×6〜8本
- 内容
600m × 6本(設定:1’50〜1’55)
リカバリー=200m jog - 解説
レース後半の苦しい場面を想定したメニュー。
600mは乳酸が溜まり始める距離であり、スピードを落とさず粘る力が鍛えられます。
後半の1kmで失速しないための耐乳酸能力アップに効果的です。
✅パターンC|スピード刺激:400m×10本
- 内容
400m × 10〜12本(設定:72〜74秒)
リカバリー=200m jog(70〜80秒) - 解説
3000mを走るには「スピードを持久力に転換する」必要があり、その基盤になるのが400mインターバル。
スピード感覚を養い、ストライド・ピッチを改善。
キレを保ちながら余裕を持って走れるフォーム作りに有効。
✅パターンD|ピラミッド走:1000→800→600→400→200
- 内容
1000m(3’10)→800m(2’30)→600m(1’50)→400m(70)→200m(32)
リカバリー=200〜400m jog - 解説
距離を短くしながらスピードを上げる形式。
「ギアチェンジ力」「リズム変化への対応力」を鍛えられるため、レースでのスパートや中盤のペース変動に強くなる。
調子を確認するスピードチェックにも最適。
✅パターンE|複合練習:1000m+400m
- 内容
1000m×3本(3’10)+400m×5秒(72秒)
リカバリー=1000mは400m jog、400mは200m jog - 解説
1000mでスタミナ系の刺激を入れた後、400mでスピード系を仕上げる二段構え。
スタミナとスピードを同日に両方刺激できる効率的なメニュー。
試合2〜3週前に取り入れるとピーキング効果が高い。
✅パターンF|変化走(ビルドアップ/レースペース走)
- 内容
(例)3000m×2本:
・1本目=9’45(3’15/km)
・2本目=9’40(3’13/km)
または、5000mビルドアップ:
・前半2500m=3’20/km → 後半2500m=3’05/km
- 解説
実際のレースを想定した「レースペース走」。
後半にスピードを上げる練習=レースでの余裕度を作る。
気持ちの切り替えとレース展開力を磨けるのが強み。
ご相談・ヒアリングは無料です。
プラン決定後、お客様にご納得いただいてから、正式なお申し込みとご入金をお願いしています。
無理なご案内や請求は一切ありませんので、ご安心ください。
※申込み後、24時間以内に必ず返事をいたします。返事がない場合はメールアドレスが間違えている可能性があります
お申込み後でも、相談・ヒアリングの結果「イメージと違った」と感じられた場合は、費用は一切ご請求いたしません。
面倒な終了手続きもありません。どうぞお気軽にお申込みください。
🏃♂️ ジョグ練習メニュー
3000mで9分台を目指すには、ポイント練習(スピード練習・ペース走・インターバル)とジョグ(つなぎの練習)のバランスがとても重要です。
1. 最重要ポイント:疲労を残さない
ジョグの日の最大の目的は「疲労を抜きつつ距離を踏むこと」です。
ポイント練習で強度の高い刺激を入れた後は、身体が回復しきらない状態です。この日に頑張りすぎると、次のポイント練習で質が落ちてしまい、結果的に力が伸びないという悪循環になります。
2.ジョグでピーキング力を養う
どのようにジョグを行うかで、次のポイント練習の調子が大きく変わります。
- 「今日はジョグを軽く流したから、翌日のポイント練習は体が軽い」
- 「ジョグで無理に距離やスピードを入れたから、翌日の練習で重かった」
こうした“軽かった・重かった”の積み重ねが、自分にとってベストな調整の感覚を養います。
これは世界大会やオリンピックを目指すトップアスリートも同じ。彼らも日々のジョグや調整の中で、「ピーキング力」=試合で最高の状態に持っていく力を磨いています。
- 「レース前にどのくらいジョグを減らすか」
- 「疲労を抜きながら走力を落とさないバランス」
を普段のジョグの中で試行錯誤することが、レース当日のベストパフォーマンスにつながります。
つまり、普段のジョグは“ピーキングの練習”でもあるのです。
3. ジョグのペース調整
ジョグは 5:00〜6:00/km程度の楽なペース が基本です。呼吸が乱れず、会話できるくらいが目安。
- 「体が重いな」と感じる日は6:00/kmでもOK
重要なのは、“ペースよりも回復度合い”を優先することです。距離を踏みたい気持ちがあっても、ジョグで追い込みすぎないようにしましょう。
4. LSD(ロングスローディスタンス)の活用
時にはジョグを「LSD」に置き換えるのも効果的です。
LSDとは?
- Long Slow Distance の略
- ゆっくり長く走る練習(例:90〜120分、5:30〜6:30/km)
- 心肺に負担をかけずに長時間走り続ける
効果
- 毛細血管が発達し、酸素を筋肉に届ける能力が上がる
- 脂肪をエネルギーとして使う能力が向上する
- フォームを安定させる「基礎作り」にも最適
👉 LSDはスピード練習の合間に入れることで、持久力の土台を厚くする役割を果たします。
✅ 1部練習の日(ジョグ中心の日)
- スピード:5’00〜6’00/km
- 時間:50〜70分(10〜14km目安)
- 目的:毛細血管の発達・回復促進・基礎持久力強化
- ポイント:ポイント練習の疲労を抜きながらも、距離はある程度踏んでおく。最後の5〜10分を少しだけペースアップ(4’40/km程度)して動きを整えるのも◎。
✅ 2部練習の日(朝+夕)
- 朝ジョグ
- スピード:5’30〜6’00/km
- 時間:30〜40分(6〜8km)
- 目的:血流促進・動き出し・疲労抜き
- ポイント:完全に「ほぐし」の位置づけ。起床後すぐなら特にゆっくりでOK。
- 夕方ジョグ
- スピード:5’00〜5’30/km
- 時間:40〜60分(8〜12km)
- 目的:有酸素強化・Eペース走の役割
- ポイント:朝よりも少しだけ速め。ポイント練習がある場合は「前日 or 翌日の疲労を考慮」して調整。
✅ 3部練習の日(朝+昼+夕)
ポイント:無理に距離を増やさず「リズム良く気持ちよく」走ることを重視。
朝ジョグ
スピード:5’30〜6’00/km
時間:25〜30分(5〜6km)
目的:体をほぐし、血流を促す。起床後ルーティン感覚。
昼ジョグ(軽め)
スピード:5’30〜6’00/km
時間:20〜30分(4〜6km)
目的:アクティブリカバリー。疲労抜きの散歩代わり。
ポイント:最も軽い位置づけ。体を動かすことで夜の練習効率を高める。
夕方ジョグ
スピード:5’00〜5’30/km
時間:40〜50分(8〜10km)
目的:一日の締め、有酸素刺激をしっかり入れる。
6カ月のフェーズごと練習具体例
6カ月~3カ月前の練習メニュー(1000m2分55秒を目指す。)
この時期はとにかくスピードを強化しましょう。
| 曜日 | メニュー | 目的 |
|---|---|---|
| 月 | ペース走4000m(12’30)+400m×1 | ペースの感覚づくり |
| 火 | 60分ジョグ+流し4本 | 有酸素回復・フォーム維持 |
| 水 | インターバル400m×4(R=200m50秒)1分10秒目安 | スピード持久力の強化 |
| 木 | LSD 70〜90分 or クロカン | 心肺・脚筋持久力の養成 |
| 金 | 40分ジョグ+補強 | 疲労抜き+体幹強化 |
| 土 | 200m×8(R=200m50秒)または600m+400m+200m | スピード刺激 |
| 日 | オフ | 回復 |
3カ月~2カ月前の練習メニュー(2000m6分10秒を目指す。)
2分55秒が達成できればスピードは十分です。そのペースを2000mまで維持できるようにしましょう。
| 曜日 | メニュー | 目的 |
|---|---|---|
| 月 | ペース走5000m(12’00~12’30)+1000m×1 | ペースの感覚づくり |
| 火 | 60分ジョグ+流し4本 | 有酸素回復・フォーム維持 |
| 水 | インターバル1000m×2(R=2分)3’10~15目安 | スピード持久力の強化 |
| 木 | LSD 70〜90分 or クロカン | 心肺・脚筋持久力の養成 |
| 金 | 40分ジョグ+補強 | 疲労抜き+体幹強化 |
| 土 | 600m×4(R=1分30)+ショート200m×3 | スピード刺激 |
| 日 | オフ | 回復 |
2カ月~0カ月前の練習メニュー(練習で3000m9分40~45秒を目指す。)
ここまでくればもうコツは掴んでいるはず。もうあと一歩。大会1週間前は練習の質を下げて疲労を抜いて仕上げていきましょう。
| 曜日 | メニュー | 目的 |
|---|---|---|
| 月 | ペース走5000m(12’00)+1000m×1 | ペースの感覚づくり |
| 火 | 60分ジョグ+流し4本 | 有酸素回復・フォーム維持 |
| 水 | インターバル2000m×2(R=3分)6’20目安 | スピード持久力の強化 |
| 木 | LSD 70〜90分 or クロカン | 心肺・脚筋持久力の養成 |
| 金 | 40分ジョグ+補強 | 疲労抜き+体幹強化 |
| 土 | 400m×8(R=1分50秒) | スピード刺激 |
| 日 | オフ | 回復 |
成功事例:YMD NEXT×RUNの実績
立ち上げ以前に、私が外部コーチ指導で指導を行った中学生や、YMD NEXT×RUN会員が、実際に3000mで9分台を達成した成功事例です。努力と適切な練習で成果を出したリアルな事例を紹介いたします。
香取市・中学2年男子(対面指導)
■成果
千葉県香取市在住の中学2年生男子。冬から春にかけての大会(約4カ月間)で、3000m10分15秒から9分47秒へ記録更新。
■第一印象
初めて会った時はおとなしく、自己主張も少ない印象でした。練習は部活動任せで、ただ漠然と走っているだけ。強みや弱点の分析もなく、練習量も不足していました。
一方で、レース展開は非常に上手で、あらゆるパターンに対応できる戦術眼がありました。
■指導内容・取り組み
・まずは現状把握と、短期・中期・長期の目標を設定
・達成可能な小さな目標を一つずつクリアしていく仕組みを導入
・練習量を増やし、距離を踏ませることを徹底
・スピード練習やジョグは私も一緒に走り、姿勢を示す指導
また、「楽しくない練習でも前向きに取り組める」よう工夫し、自主性を引き出すことを意識しました。
■成果・成長
指導の中で本人も少しずつ変化。部活以外で自主練を行うようになり、自分の意見を伝えられるようになりました。
結果として、3000m9分台を達成し、他種目でも県大会準決勝進出。さらに、高校も陸上推薦で進学が決定。記録だけでなく、人としての成長も大きく感じられた事例です。
岡山県・中学3年男子(オンラインサポート)
■成果
岡山県在住の中学3年生男子。オンラインサポートを継続中。
3000m9分45秒から9分34秒まで短期間で伸び、目標の9分30秒切りが目前。
■第一印象
やる気に満ちあふれ、練習量も豊富。練習ノートもきちんと記録し、「強くなりたい」という思いが強く伝わってきました。
ただし、毎日追い込みすぎて疲労が蓄積しているのが課題で、このままでは伸び悩む危険性があると感じました。
■指導内容・取り組み
・ポイント練習とジョグのメリハリを徹底
・特にジョグが速すぎる傾向があったため、ペースを落とすよう繰り返し指示
・「1週間だけでいいから完全に指示に従ってみよう」と提案し、過度な不安を和らげる工夫
・練習報告や相談を毎日してくれるので、その情報をもとに的確なアドバイスを提供
やる気が強すぎるためブレーキをかけるのが大変でしたが、徐々に疲労コントロールができるようになり、練習の質が向上しました。
■成果・成長
ジョグで疲労を抜けるようになると、スピード練習で体が軽く動き、内容の濃い練習が可能に。結果として、一気に記録が伸びて9分30秒切り目前まで成長しました。現在も継続中で、さらなる飛躍が期待されます。
この2つの事例はタイプこそ正反対ですが、共通しているのは「課題を正しく見極め、適切な指導を継続した結果、確実に成果につながった」という点です。
どんなタイプの選手でも、正しいアプローチを続ければ必ず伸びていきます。
福島県・中学2年男子(オンラインサポート)
■成果
福島県在住の中学3年生男子。オンラインサポートを継続中。
3000m10分15秒から9分50秒まで更新し、目標の9分59秒切りを早々に達成。さらに次のレベルを目指して取り組みを続けています。
■第一印象
やる気にあふれ、走行距離も十分にこなしている努力家タイプ。
派手さはないものの、おとなしい中に闘志を秘めた選手という印象でした。
■悩み
一生懸命練習をしているのに、なかなか成果が出ないのが課題。特にスピード練習が苦手で、力を発揮できずに悩んでいました。
■指導内容・取り組み
練習内容を分析すると、ジョグのペースが速く、距離は十分に踏んでいる一方で、スピード練習の設定タイムが合っていないことがわかりました。
そこで次の改善策を実施しました。
・練習量を20%削減し、疲労を軽減
・ジョグは6:00/kmペースを徹底し、負荷を調整
・スピード練習は本数を3分の2に減らす代わりに、設定タイムを大幅に引き上げ
従来:
・1000m×4本(3’30/km)
・400m×15本(1’25)
・2000m×3本(7’00)
改善後:
・1000m×2本(3’15/km)
・400m×7本(1’15)
・2000m×2本(6’40)
このように「量を抑え、質を上げる」練習に切り替えました。
■成果・成長
改善の効果はすぐに表れ、苦手意識のあったスピード練習にも手応えを感じるように。結果、3000mで9分50秒を達成し、安定して9分台で走れる力を獲得しました。
今では「スピード練習が得意」と言えるほどに成長しており、さらなる飛躍が期待される選手です。
Q&A (よくある悩み)
実際にYMD NEXT RUNの会員の方々から多く寄せられた悩み――「疲労が抜けない」「ペースが安定しない」「練習期ごとの調整がうまくいかない」など――に対して、取り組んだ工夫や改善事例を公開しています。
体づくりに大事な食事
中学生は成長期まっただ中。走ることに加えて、以下も意識しましょう。
- 食事(特に鉄分・タンパク質)
- 睡眠(8〜9時間)
- 休む勇気
も大切です。「疲れてるな」と感じたら、ジョグや補強だけの日にしてOK。週1~2日は「疲労回復優先日」を設けると長く強くなれます。
✔️ 食事の基本バランス(PFC)
- P(たんぱく質):体の修復と成長(鶏むね肉、卵、納豆)
- F(脂質):ホルモン・細胞膜の材料(オリーブ油、ナッツ)
- C(炭水化物):エネルギー源(白米、パスタ、果物)
✔️ タイミングも意識!
- 練習後30分以内のリカバリー食(プロテイン+バナナなど)
- レース1〜2日前のカーボローディング
- 試合当日の朝食:低脂質+高糖質(おにぎり、バナナなど)
✅食事について、以下の記事で詳しく書いているので、合わせて読んでね↓↓
関連記事|継続のカギは「休養と回復」にもある
ランニングを楽しく続けるためには「走ること」だけでなく、「休むこと」も大切です。無理に走り続けてしまうと、ケガやモチベーション低下につながり、せっかくの努力が水の泡になることも…。
以下の記事では、ランナーにとって欠かせない リカバリー(疲労回復・休養法) について詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
食事と睡眠について、以下の記事で詳しく書いているので、合わせて読んでね↓↓
すべてはここ!継続!
3000mで9分30秒を切るというのは、簡単ではありません。しかし、正しい方向で努力を積み重ねれば、決して不可能なタイムではないということも事実です。
焦らず、日々の練習を振り返り、徐々に自分の力を引き上げていく。その継続がやがて自信となり、レースでの力になります。
継続と努力が、あなたを記録更新へと導きます。
🔑 継続のために効果的な工夫
上記のステップと同じことになってしまいますが、継続のためには以下の工夫が大事です。
- 練習ノートを毎日つける
- 体調や気づき、良かった点・反省点を記録することで、モチベーションの維持につながる
- 短期目標を立てて、達成の喜びを感じる
- たとえば「今月中に1000mで3分05を切る」など
- 仲間と刺激を与え合う
- 一人では難しくても、仲間の存在は大きな励みになる
- 調子が悪い日は“休む”選択肢も持つ
- 無理して続けると故障や燃え尽きに繋がるため、「休む勇気」も必要
- 憧れの選手や将来の目標を視覚化する
- 部屋やスマホに貼っておくと、自分を鼓舞できる
- YMD NEXT×RUNを利用する。
継続とは、「気合い」だけではなく環境と仕組みの設計です。小さな積み重ねがやがて大きな結果に繋がります。焦らず、地道に、自分を信じて続けていきましょう。
- 月に1回はタイムトライアル(1500m or 3000m)を実施
- レース2週間前からは「調整期」として強度を下げる
- 自信を持ってスタートラインに立つための「準備」が大事
継続について、以下の記事もおすすめです。
ランニングを継続するための黄金ルール|楽しく走るための実践法 – YMD NEXT×RUN|オンライン・ランニングサポート
レース直前2週間の過ごし方
調子を本番にピークさせるために、直前の2週間は練習の「質」と「量」を調整していきます。
調子がいい時、悪い時、大会が近づくにつれ、練習をやりたくなりますが、我慢して抑えましょう。
- 2週間前:1000m×3(レースペースで)+ジョグ多め
- 1週間前:2000m+1000m(レースペース確認)
- 3日前:軽いレペ(400m×3〜5)
- 前日:完全休養 or 軽ジョグ+流し
直前期は「疲労を抜きつつ、動きを失わない」バランスが大切です。
✅レースについて、以下で詳しく書いているので、合わせて読んでね。
最後に
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。筆者は駒澤大学・富士通陸上部での競技経験を活かし、地元・香取市を拠点に「YMD NEXT×RUN」というクラブを運営中。中高生のエリート育成から一般向けの練習サポートまで幅広く行っています。
練習相談やパーソナル指導をご希望の方は、公式ホームページをご覧ください。
ご相談・ヒアリングは無料です。
プラン決定後、お客様にご納得いただいてから、正式なお申し込みとご入金をお願いしています。
無理なご案内や請求は一切ありませんので、ご安心ください。
※申込み後、24時間以内に必ず返事をいたします。返事がない場合はメールアドレスが間違えている可能性があります
お申込み後でも、相談・ヒアリングの結果「イメージと違った」と感じられた場合は、費用は一切ご請求いたしません。
面倒な終了手続きもありません。どうぞお気軽にお申込みください。


\38歳・3児のパパランナー/
2011年に現役を引退後、会社員として働きながら、市民ランナーとしてランニングを継続。
これまで「人の役に立ちたい、力になりたい」という思いから、外部コーチやクラブサポートとしても活動してきました。ある日、ゲストとして参加したランニングチームで多くの市民ランナーと出会い、皆さんの熱意と悩みに触れたことで、「この私でも誰かの力になれる」「もっと多くの人の役に立ちたい」と強く感じました。
その想いから、オンラインランニングサポート「YMD NEXT×RUN」を立ち上げ、現在は一人ひとりに寄り添うパーソナルサポートを展開中です。
【実績・経歴】
〇山田中学校
県大会優勝、県駅伝区間賞
〇市立船橋高校 (体育科専攻)
県大会優勝、インターハイ出場
〇駒澤大学 (文学部心理学科専攻)
2009年箱根駅伝第4区出場、関東インカレ決勝進出
〇富士通
大田原マラソン第3位、パリマラソン17位(アジア1位)